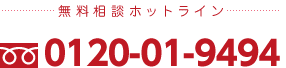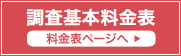|
|
第32弾 養育費の決め方は?たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第32弾です。
現在、日本の離婚の9割は協議離婚ということもあり、
当事者間で養育費の金額を決めるケースが多いようです。 当事者間で話し合いをして、支払方法(期日、振込方法)や
期間(子供が何歳になるまで)、進学した場合、増額するか どうかを細かく決め、「公正証書」などの署名にしておく ことが非常に重要です。 しかし、これから子供が成長するまでに、どれくらいの
費用がかかるのか、話し合いで決めるのはたいへん難しい ですよね。 もしも、当事者間の話し合いで決めることが出来なければ、
家庭裁判所で決めてもらうことになります。 家庭裁判所では、東京と大阪の裁判官の共同研究の結果、
2004年3月に「東京・大阪養育費等研究会」が発表され、 養育費、婚姻費用の算出方法と算定式に基づいて養育費 を算出できる『養育費算定表』が作成されました。 これは、養育費を請求する側「権利者」と払う側「義務書」
の年収金額を基礎とし、子供が養育費を払う側と同居したと 仮定すれば、子供の為にどのくらいの生活費が必要なのか 計算し、「権利者」と「義務所」の収入の割合で分けて 「義務者」の支払うべき養育費の額を決定するという ものです。 この養育費算定表は、子供の人数(1〜3人)と年令
(0〜14歳と15〜19歳の2区分)に応じて表1〜9に 分かれており、「権利者」と「義務書」の年収金額、 子供の年齢と人数を当てはめれば、養育費の目安が 容易に分かります。 この算定表は、あくまで標準的な養育費を簡易迅速に算定する
ことを目的として作成されたものです。 ですから、最終的な養育費の金額については、いろいろな事情 を考慮して、当事者の合意で自由に定めることができます。 では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海 utsumi@galu-shikoku.com |
第33弾 一度決めた養育費を変更できるか?たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第33弾です。
養育費を支払う期間、「子供が成人になるまで」と取り決められる
ケースが多いので、10〜20年にわたることも珍しくありません。 それ程の長期間になると、支払う側も受け取る側も色々と
状況が変化していきます。 このような場合、養育費を取り決め後でも、
養育費の増額、減額、免除を請求することができます。 例えば、物価水準の上昇、子供の学費の増額、医療費の
支払いなどにより、養育に必要な費用が増大する場合は 増額請求を、 支払う側の親の失業や病気などにより、支払い能力が 低下した場合には減額請求をすることができます。 また、受け取る側の親が再婚し、再婚した相手と子供が
養子縁組をした場合、養育費の減額または支払い義務の 免除を請求することができます。 養育費を決めた契約時に予見できなかった下記のような
事情の変化があった場合には、養育費の変更が可能な 場合があります。 ■減額の事情
1.支払う側の病気 2.支払う側の転職、 3.失業による収入の低下 4.受け取る側の収入増 などが、考慮されます。 ■増額の事情
1.入学、進学に伴う費用 2.病気や怪我による治療費 3.受け取る側の病気や怪我 などが、考慮されます。 養育費の額を変更したい場合は、まず父母で話し合う
ことになります。 話し合いがつけば、金額は自由に変更できます ↓ もしも、父母で話し合いがつかない場合は、家庭裁判所に 調停を申し立て、養育費の額の変更を求めます。 調停は父母どちらから申し立ててもかまいません。 申し立て方法については養育費の支払い請求の場合と同じです。 ↓ 調停で話し合いがつかない場合は審判に移行し、 裁判所が養育費の増減を決定します。 しかし、審判などで養育費の変更が認められるのは あまり簡単ではありません 「ただ単に、減らして欲しい」という理由では 認められません。 また、離婚時に「養育費を請求しない」という取り決めを
していたとして、子供自身からの親に対する扶養料の請求権 は親が勝手に放棄することは出来ません。 では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海 utsumi@galu-shikoku.com |
第34弾 離婚しても、子供とはいつでも会えるのか?たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第34弾です。
夫婦の離婚が成立した後、
親権者または監護者になれなかった親が子供と会ったり、 一緒に遊んだりすることが出来ます。 面接交渉の決め方には、
日時や場所、回数など具体的な条件を協議にて定める「協議型」 と、具体的な条件を細かく決めておく「執行型」があります。 「執行型」では、以下のような条件をあらかじめ定めておきます。
○月に何回、何日、何時間会わすか ○誰が日時を決めるのか ○宿泊の有無 ○会わせ方、会う場所 ○電話や手紙のやり取りの有無 ○学校行事への参加の有無 ○子供の受け渡し方法 ○子供との連絡方法 等々 一般的には、「協議型」が多いようですが、「執行型」
にした方が良い場合もありますので、子どもの年齢や 配偶者との関係により選択されるとよいでしょう。 また、「一定の年齢になるまでは面接交渉はしない」
「親権者が同伴する」等の条件を付けることも可能です。 別居や離婚などで子どもと離れて暮らす親が、子供と交流や
面接を持つ権利は、判例や家庭裁判所の実務でも認められて います。 ですから、もしも面接交渉を拒否された場合は、
面接交渉の調停や審判を申し立てることができます。 面接交渉は、親の権利であるとともに、子供の権利でも
あると考えられています。 しかし、
いくら接交渉権があるといっても、無制限に認められる わけではありません。 子供の利益に反すると判断された場合、又は下記のような
場合は制限されることになります。 ○アルコール依存症など、子供に悪影響を及ぼす 可能性がある ○養育費をきちんと支払わない ○親権者や子供に対する暴力、虐待等 ○子供が嫌がっている場合 ○復縁を迫ったり、憤まんをぶつけるためなど、 面接交渉自体が別の目的にあたる場合 ○面接後に子どもが情緒不安定になるなど悪影響が ある場合 等々 親権者としては、
「絶対会わせたくない」「話しをさすのもイヤ」 「子供に対する悪影響が心配」など、さまざまな理由があります。 しかし、離れていても子供にとっては大切な親であることに 変わりありません。 子どもにとって、一番ベストな生活環境を子どもの目線で考えて あげましょう。 では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海 utsumi@galu-shikoku.com |
第35弾 離婚後の親子の姓はどうなるのか?たんてい おやびんの内海(うつみ)です。
本日は「1日、3分ずつで分かる離婚の法律」の第35弾です。
結婚により、姓を変更した妻は、
離婚をした場合には、婚姻前の旧姓に戻ることが原則です。 戸籍に関しても、婚姻前の戸籍に戻ることになります。 しかし、
婚姻中の姓を名乗りたい場合は、離婚の日から 3ヶ月以内に、【離婚の際に称していた氏を称する届け】 を市区町村役場の戸籍課に届出すれば可能です。 (元の配偶者の承諾は必要ありません。) 3ヶ月が経過した後、この届出をしようとする場合は
家庭裁判所の許可が必要となります。 ただし、
子供の姓に関しては、 両親が離婚して姓が変わったとしても、 子供の姓は両親が婚姻中に称していた姓のまま というのが原則です。 ですから、
妻が子供を引き取り、親権者になったとしても、 何も手続きをしなければ、子供の姓は元のままで 元夫の姓を名乗ることになります。 せっかく、親権を得て、同居して育てているのに
姓が違うという困った事態になってしまいます。 また、戸籍も別れた元夫側に入ったままという ことになってしまう場合もあります。 そこで、
家庭裁判所に【子の氏の変更許可の申立書】を 提出します。 家庭裁判所の許可がおりれば、自分の戸籍に
入籍させる「入籍届」を市区長村役場に提出し、 親子が同じ姓、同じ戸籍になります。 子供が15歳未満の場合なら、親権者がこの手続きを
を行なうことが出来ます。 しかし、
子供が15歳以上の場合は、 「子供本人が姓を変えるかどうかを決めることが出来る」 ので、子供本人が申し立てを行なわなければなりません。 また、子供の姓の変更を行なったあとでも、
子供が20歳になってから、1年以内であれば、 「入籍届」を提出すれば自分の意思で元の姓や 戸籍に戻ることができます。 離婚後に「子供の姓を変えたい」と思っても、
子供にも学校生活があるので、そのことも 十分考慮して考えてあげましょう。 では、また次回
感想やご質問などございましたら遠慮なくご連絡下さいね
たんてい おやびん内海 utsumi@galu-shikoku.com |